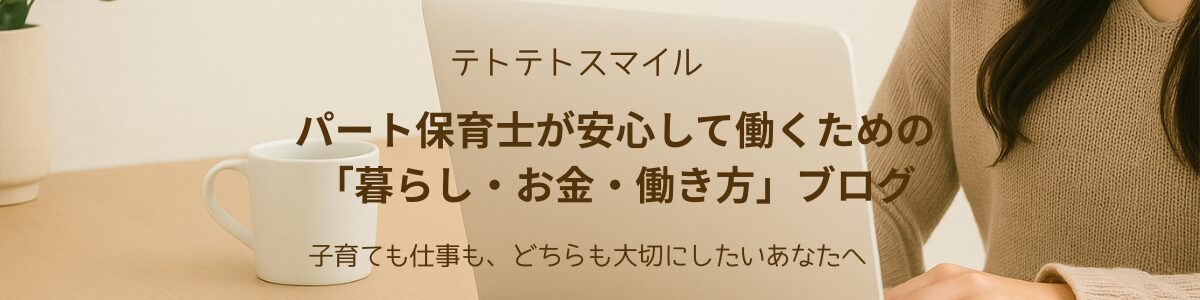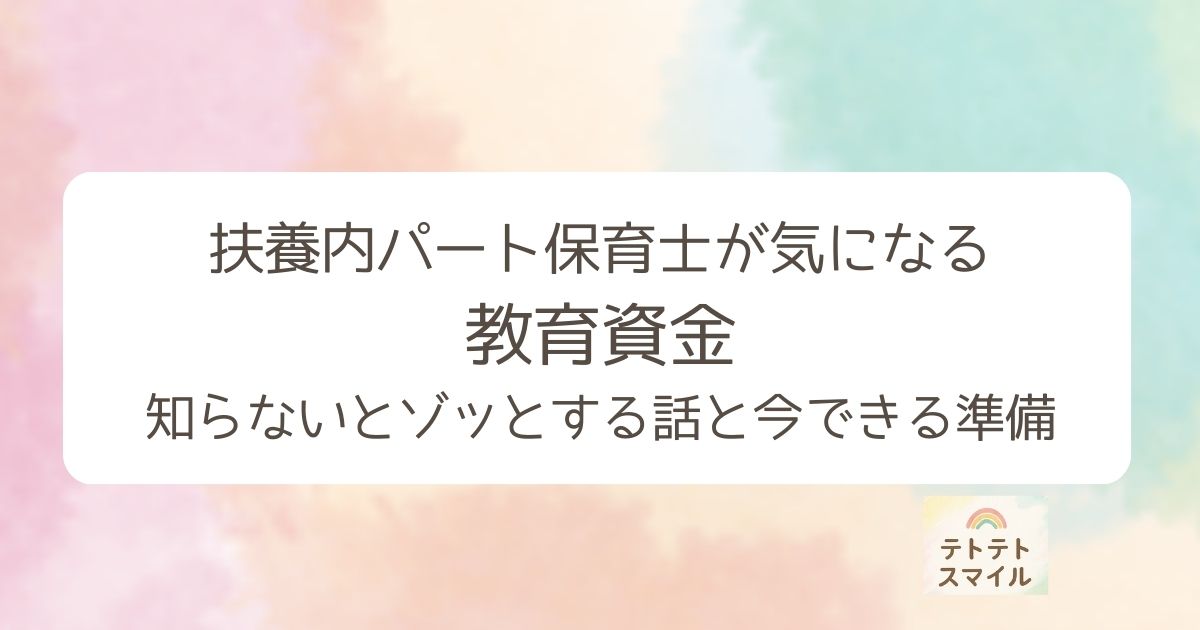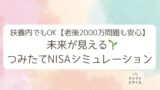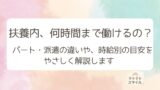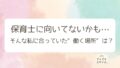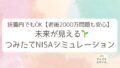※このページはアフィリエイト広告を利用しています。
教育資金って、実際どのくらい必要なの?
知らないままだと危険かもしれません。
私も1年前までは「まあなんとかなるでしょ」と思っていましたが、実際に数字を知ったとき、一瞬ゾッとしました。
でも大丈夫。
知ったからこそ安心できる準備も始められました。
この記事では「教育資金にかかるお金の全体像」と「扶養内パートでもできる準備法」を、私の体験もまじえながら分かりやすくまとめます。
この記事をかいている人:tomako
保育は好き。
でも、わが子の「おかえり」に間に合いたい──。
そんな想いから働き方を見直しました。
2児の母であり、保育士・幼稚園教諭1種・FP3級。
資格と体験をあわせて、保育士の「働き方とお金の不安」をやさしく解説しています。
教育資金ってどのくらい必要?

※教育費=実際にかかるお金のことです。この教育費に備えるために準備するお金を「教育資金」といいます。
| 公立(年間平均) | 私立(年間平均) | |
|---|---|---|
| 幼稚園 | 約18.5万円 | 約34.7万円 |
| 小学校 | 約33.6万円 | 約182.8万円 |
| 中学校 | 約54.2万円 | 約156万円 |
| 高等学校(全日制) | 約59.8万円 | 約103万円 |
| 授業料/年 | 入学料 | 施設設備費 | 初年度納付金(合計) | 4年間合計(決め) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 国公立大学 | 約54万円 | 約28万円 | – | 約82万円 | 約240万円 |
| 私立大学(文系) | 約96万円 | 約24万円 | 約16万円 | 約148万円 | 約400万円 |
| 私立大学(理系) | 約130万円 | 約25万円 | 約30万円 | 約185万円 | 約520万円 |
参照:文部科学省私立大学等の平成30年度入学者に係る学生納付金等調査結果について
大きな金額の数字だらけで嫌になりますよね・・・
簡単にまとめると
◆公立メインの場合
→ 約1,000万円前後
◆私立が多い場合
→ 2,000万円以上
| 公立 | 私立 | |
| 小学校6年間 | 約200万円 | 約900万円 |
| 中学校3年間 | 約150万円 | 約400万円 |
| 高校3年間 | 約150万円 | 約300万円 |
| 大学4年間 | 約250〜500万円 | 約400〜800万 |
ここからさらに「自宅から通うか・下宿か」でも費用は大きく変わります。
下宿になると生活費もプラスされて、正直ゾッとしますよね…。
でも「全部を一度に準備しなきゃ!」と焦る必要はありません。
教育資金は段階ごとに備えていけば大丈夫。
全体像を知っておくだけで安心につながります。
扶養内パート保育士にできる教育資金の準備
数字をみて我が家には無理無理・・って思った方も大丈夫。
教育資金を考えるときに大切なのは、今の家計をきちんと把握すること。
「なんとなく余ったら貯金」では、思うようにお金は貯まりません。
家計簿をつけよう

私はノートの家計簿は三日坊主で続かず…。
でも家計簿アプリ(私はマネーフォワードME)を使ったら、自動で数字が出るので「ここにこんなに使ってたんだ!」と気づけました。
ズボラな私でも続けられたのはアプリのおかげ。
方法はなんでもOKですが、まずは収支を“見える化”するのが第一歩です。
私が使っているアプリはこちら。マネーフォワードME
無料です。
カードと連携させて、自動で集計してくれるのでとっても簡単。
最近、家計簿アプリはたくさんあるので、自分にあったアプリをみつけてくださいね。
児童手当はそのまま教育資金へ
毎月の家計に使ってしまうと意外と消えてしまう児童手当。
最初から教育資金専用口座に入れると、「貯めている」実感につながります。
「この口座は教育資金だけ」と決めると、数字が分かりやすく、モチベーションも続きやすくなります。
子どもの未来のために、頑張りましょう。
学資保険からNISAへ切り替えた体験
以前は「教育資金といえば学資保険」と思って契約していました。
でもお金のことを学びだし、保険の仕組みを知り、思い切って解約。
その分をつみたてNISAに回すことにしました。
最初はドキドキでしたが、“知って選び直せた”ことが今は安心につながっています。

扶養内パートで稼いだお金から少し 教育資金へまわそう
扶養内パートで稼いだ額のうち、少額でもいいので教育資金にまわしましょう。
ちょっとしか稼いでないから意味ないんじゃない?と思うかもしれませんが、
チリも積もれば山となる です。
「毎月◯円ずつ積立NISAで積み立てた場合」などのシュミレーションを見ることができます。
これ、面白いし、増える未来がイメージできるので、ぜひ一度やってみてください✨️
【教育資金】私の学びと気づき
私はずっと「教育資金って、なんとかなるでしょ」と思っていました。
でも数字を知ったとき、一瞬ゾッとしたんです。
ただ、そこで終わりではなく「知ったからこそ安心につながる準備ができる」と考え方が変わりました。
学資保険を解約してNISAに回したことも、最初は不安でしたが「知らないまま続けるより、自分で選び直せた」という経験になりました。
お金の知識を学んだことで、教育資金だけじゃなく老後や保険のことまで、暮らし全体を見直すきっかけに。
“知らない”ことが一番の不安材料で、“知ること”が安心につながるのだと実感しました。
教育資金・お金の不安が整理できた本
そんな私にとって大きなきっかけになったのが、『お金の大学』という本でした。
難しい専門書ではなく、イラストや図解が多いので、一般庶民の私でも「めちゃわかりやすい!」と思えた1冊です。
教育資金のことだけでなく、老後・保険・扶養の壁など、暮らし全体のお金の不安を整理できます。
辞書のような存在です。
「ふんわり不安はあるけど、まだ何もしてない」という方にこそ、ぜひ読んでほしい本です。
これ一冊で「知らないまま」から「知って安心へ」と気持ちを切り替えられるはず。
不安を減らすための最初の一歩に、本当におすすめです。
ちなみに、子ども向けのマンガもあります。
親子で一緒に読めるので、“お金のことを家庭でどう伝えたらいい?”と悩んでいるママにもぴったり。
ママ自身には『お金の大学』、子どもと一緒に学ぶならマンガ版。
どちらも、不安を安心に変えてくれる心強い一冊です。
お金の知識があれば、教育資金の安心につながる

教育資金って「ふんわり不安だけど、まだちゃんと考えていない」という人も多いと思います。
でも実際に数字を知ると、一瞬ゾッとすることもありますよね。
ただ、“知ること”が不安を大きくするのではなく、安心につながる第一歩。
家計簿で今の暮らしを見える化して、児童手当やNISAなど、自分に合った方法で少しずつ備えていけば大丈夫。
私も1年前は「なんとかなるでしょ」と思っていましたが、学んで行動を変えたことで安心感を持てるようになりました。
あの日、気づけた自分を褒めてあげたい。
あのまま知らずに過ごしてたらと思うと正直こわい。
今できることを一歩ずつ。
各家庭にあった方法をみつけてくださいね!